| 翻訳と日本の近代 丸山真男 加藤周一 著 岩波新書 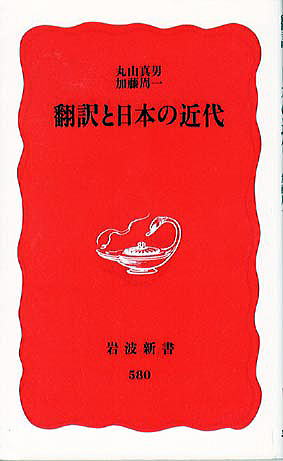 先日、テレビで、日本企業が海外進出する際に、日本の価値観や手法を持ち込んでしまったために、伸び悩んでしまうという事例が出ていた。そのため、企業もようやく現地の人を幹部候補生として雇い始めた。同時に、若い優秀な社員をどんどん外国へ送り出しているという。外国で奮闘する人々は、現地の人と同じ視点になって気が付くことは多いと語る。 まったくの余談だが、以前、海外へ出張する機会があり、赴任中の日本人に、「お世話になったお礼に、日本からなにか送りますよ。リクエストありますか?」と聞いたら、「話し相手…」と本気で言われた。華やかに見える海外赴任も大変なんだなぁ、と涙ぐんでしまった、20代の私である。 …話を戻す。本社が日本にあっても、公用語が英語となる会社も出てきた。いずれにせよ、日本の商品の国際競争力が落ちてきているといわれるなかで、企業も必死になっているのだろう。戦いの場は世界なのだから、頭のチャンネルを否が応でも切り替えなければならない。 幕末、攘夷から開国へ転じた日本も、チャンネルの切り替えを迫られた。もちろん、ショックは比べようもないほど大きかったはず。これまで外国=中国、ポルトガル、朝鮮くらいだったのが、さらにアメリカ・フランス・イギリス…と一気に世界が広がっていく。とりあえず、相手の情報ほしさに、人を留学させ、あらゆる分野の書物を翻訳しまくる。 開国へ転じたきっかけは、武士の国ニッポンが薩英戦争で,コテンパンにやられた危機感だったらしい。漢文に親しんだ経験から、「文明を理解することは歴史を理解すること」という中国儒家の文化的習慣のあった当時の人々は、相手の歴史的背景を知ることから入っていった。漢文を読む習慣がなくなるにつれて、そのような文化的習慣も薄れ、現代主義と実用主義が蔓延してきてしまったと、本書で丸山氏が嘆いている。 つまり、当時の人たちは、ものすごく広い分野の情報を得たうえで、日本の方向性を模索していった。だからこそ、世間知らずだった日本が近代国家の階段を上っていけた。現代の私たち、もう一度謙虚に、漢文からみっちり勉強しなおしたほうがいいかもしれない。(真中智子) |
|---|